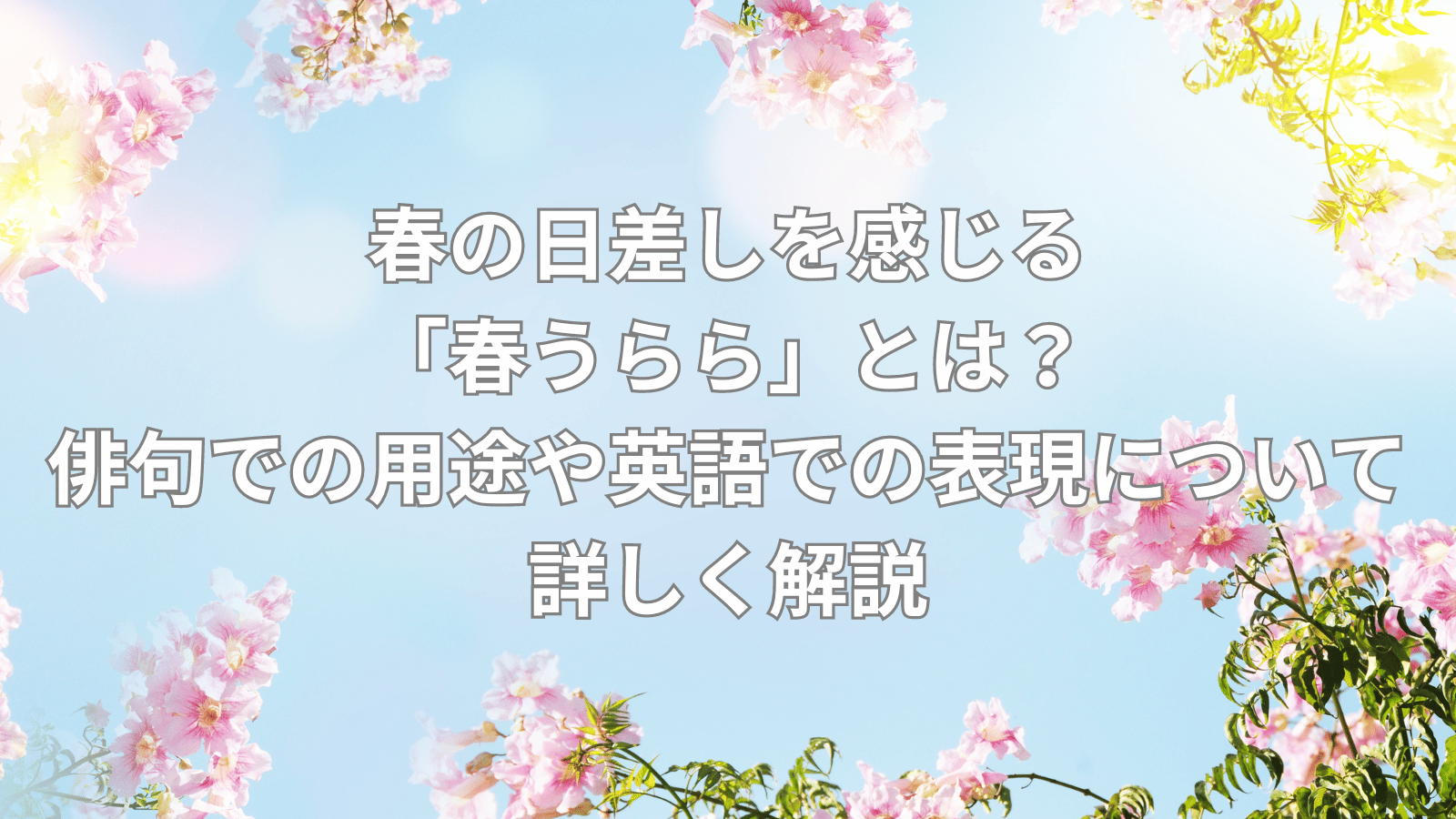多くの方が「春うらら」という言葉から心地よいイメージを抱くかもしれませんが、その具体的な意味を説明するのは少し複雑です。
他にも「秋うらら」や「冬うらら」といった季節を表す表現がありますが、それぞれにどんな意味があるのでしょうか。
この記事では、以下の内容を詳しく説明していきます
- 「春うらら」の語源と意味
- 「うらら」と「のどか」の違い
- 「春うらら」の類語
- 「春うらら」の使い方
- 「うららか」を使った俳句
- 「秋うらら」や「冬うらら」の意味
- 「春うらら」の英語表現
春うららの意味
「春うらら」とは、春の空が晴れ渡り、穏やかな日差しが降り注ぐ様子を表す言葉です。
この表現は、名詞「春」と形容動詞「うらら」が組み合わさっており、「春麗ら」と漢字で表記されることもあります。
うらら(麗ら)の意味と語源
「うらら」とは、古語の「うらうら」という言葉の省略形で、「日差しが柔らかく照る様子」や「心が穏やかであること」を意味します。
この言葉は「ゆらゆら」という表現が変化したものだとされ、その穏やかな響きが特徴です。
また、「うららか(麗らか)」としても使われます。
麗らか(うららか)とは何か?
「うららか(麗らか)」という言葉には、3つの異なる意味があります
- 空が晴れて、日が柔らかく照る様子。
- 声が晴れやかで明るく、活気がある様子。
- 心にわだかまりがなく、すっきりとした、またはおだやかな心境。
「うららか」という言葉は、天候や動物や人の声、そして人の心の状態に対して使われます。例えば、次のような文で使うことができます
- 春のうららかな陽気に誘われて散歩に出かける。
- 春を祝うかのように小鳥がうららかに鳴く。
- 親の優しい言葉で心がうららかになる。
「うらら」という言葉も「うららか」とほぼ同じ意味ですが、特に春の天気について言及する際によく使われます。
「うらら」と「のどか」の違い
「うらら」とよく似た意味を持つ「のどか(長閑)」という言葉もあります。
「のどか」も晴れた天気で穏やかな状態を指しますが、細かな違いがあります。
「うらら」は「穏やかな日光」によって心地良い状態を指し、「のどか」は人が置かれている穏やかな環境や風景からくる心地よさを表します。
「のどか」はまた、「静かでゆっくりとした時間を過ごす様子」をも意味し、「長閑」という漢字が示すように「長く静かな状態」のニュアンスも持ちます。
要するに、「うらら」は日光による心地よさを、「のどか」は穏やかな環境による心地よさをそれぞれ表しています。
春うららに似た言葉たち
「春うらら」とよく似た表現には以下のような言葉があります。
- のどか(長閑)
- 小春日和(こはるびより)
- ほがらか(朗らか)
「小春日和」は、春を連想させる表現ですが、実際には11月から12月初旬の暖かく穏やかな日を指します。
「ほがらか」は、日が明るく晴れ渡る様子、心にわだかまりがなく明るい気持ちになること、広々として明るい状況を表します。
春うららを使った例文
ここでは「春うらら」を使用した具体的な文例を紹介します。
- 今日は春うららで、ピクニックにぴったりの日和です。
- 春うららの陽気に誘われて、思わず眠気が襲ってきました。
- 冬の寒さが去り、春うららのような暖かな日が続いています。
春うららと季語としての使い方
実は「春うらら」という季語は存在しませんが、春の季語として使う場合の表現をご紹介します。
時候の挨拶での春うらら
時候の挨拶で「春うらら」を表すときには、次のような言葉が適切です。
- 麗日の候(れいじつのこう)
- 春光うららかな季節を迎え
- うららかな好季節を迎え
- うららかな春日和の頃
- 春陽麗和(しゅんようれいわ)の好季節
「麗日」は「うららかな春の日」を意味し、春全般に使える季語です。
「春陽麗和」は「春の日差しが暖かく心地良い」という意味を持っています。

俳句における春の表現
俳句では、「うららか(麗らか)」は春を象徴する季語として扱われます。そのため、春の情景を描く際には以下の言葉が使われます。
- うららか
- うらら
- うらうら
- うららけし
- 麗日
これらの語は、春の気配を表現する際に選ばれることがありますが、「春うらら」という表現自体は厳密な季語の用法ではなく、その音韻の美しさから使われることもあります。
ただし、この用法は一部で正式な季語の使用とは見なされないこともありますが、詩的な響きを重視する場合には認められることもあります。
「うららか」を用いた俳句の紹介
以下に、「うららか(=春うらら)」という春の季語を活用したいくつかの俳句を紹介します。
これらの句は、春の温かな日差しや自然の美しさを巧みに表現しています。

秋うらら・冬うららって?
普通、「うらら」と言えば春の季節によく使われる言葉ですが、秋や冬にも「秋うらら」「冬うらら」という表現があります。
秋うらら(秋麗)
「秋うらら」は通常「秋麗」と表記され、「しゅうれい」と読まれることもあります。
この言葉は秋の晴れ渡った日に春のような心地よい穏やかさを感じる様子を表し、秋の季語(三秋)として使われます。
10月の時候の挨拶に「秋麗」を使うのが一般的で、涼しさが訪れるこの時期にピッタリの表現です。
なお、「春麗」を「しゅんれい」と読むことは少ないです。
冬うらら(冬麗)
「冬うらら」は一般に「冬麗」と表記され、「とうれい」と読まれることもあります。
この言葉は冬の晴れわたる日差しの中で春のような穏やかさを感じる様子を意味し、冬の季語(仲冬)として分類されます。
冬の時候の挨拶に「冬麗」は通常含まれませんが、親しい人への手紙などで季節の雰囲気を伝えるのに使うと良いでしょう。

例えば、「寒さが厳しい季節ですが、冬麗を感じる日々が続いています」といった表現が適しています。1月の挨拶では「うららかな初日の光を仰ぐ」といった、祝いの場にふさわしい言葉がよく使われます。
春うららの英語表現
「春うらら」を英語で表すと、以下のようになります
- “a clear and mild spring day”(晴れて穏やかな春の日)
- “a beautiful spring day”(美しい春の日)
春うららの意味全体
「春うらら」とは、春の晴れた空と穏やかに輝く太陽を表す日本語です。
「春うらら」は春の季語として、時候の挨拶や俳句に使われます。
「春うらら」は穏やかな日差しの中で感じる心地よさを、「のどか」は静かで穏やかな時間や環境から来る心地よさを表します。
また、「春うらら」の類語には「のどか」、「小春日和」、「ほがらか」などがあります。
他にも「秋うらら(秋麗)」や「冬うらら(冬麗)」といった季節を表す言葉もあります。
ご紹介した内容で、春の明るく穏やかな日差しを表す「春うらら」の魅力について理解が深まったことと思います。
また、「春の~うららの~隅田川~♪」という歌詞で始まる「花」という曲は、滝廉太郎が作曲したもので、「四季」の一部です。
この曲集には他に「納涼」、「月(秋の月)」、「雪」が続きます。
特に「花」は、源氏物語の一節が元になっており、その和歌「春の日のうららにさして行く船は、棹のしずくも花ぞちりける」は春の日の美しさを詠んだものです。
「うらら」という言葉は、その柔らかな響きと共に、穏やかな春の日を完璧に象徴する言葉と言えます。